きことわは、2011年の芥川賞受賞作だが、同時に受賞した苦役列車が話題になり、こちらの作品はあまり話題にならなかった記憶がある。
実際、本屋で他の本に並んで棚に刺さっているの見た時、きことわ?聞いたことある、、、けど、何だっけ?という感じだった。
あらすじ
あらすじ
永遠子は夢をみる。貴子は夢をみない。葉山の高台にある別荘で、幼い日をともに過ごした貴子と永遠子。ある夏、突然断ち切られたふたりの親密な時間が、25年後、別荘の解体を前にして、ふたたび流れはじめる―。第144回芥川賞受賞。
夢見る熟女の百合小説
感想は、下記のたまごまごさんの記事が核心を突いていると思う。一言で言えば、夢見る熟女の百合小説なのだ。

この貴子と永遠子の関係が、えらい萌えるんだな。幼い時のシーンはもう完全にキャッキャウフフですよ。「きこちゃん」「とわちゃん」とか呼ぶひらがな文字が紙の上に浮かぶだけで、その声が聞こえるかのようでキュウウンってなります。(中略)
永遠子にまつわる文章が非常に言葉ひとつひとつがふわふわしていて、結婚して母でありながら、まったくもって中身が少女しているんですよ。まー永遠子の夢見がちなこと。(中略)
というかこれ四十歳の夢見がちな少女だよ。お互いの体温感じて過去に思いを馳せるとかたまらんよ。「女の子二人」をよく理解してないとこれは書けない!あー萌えた。
例えば、本文ではこんな感じだ。
このまま夢の中で過ごし続けることになったとしても永遠子は構わなかった。これから先に起こったはずの出来事も、この夏を機に貴子と会わなくなることも、夢の中の永遠子は知っている。一生目覚めず、やがて夢の中の永遠子が外の自分の歳を追い越して行くとしてもかまわなかった。
純文学か、それとも美しい追憶に耽溺するポルノか
ニューシネマ・パラダイスで、アルフレードは落ち込むトトに「若いのだから外に出て道を探せ、村にいてはいけない、そして帰ってきてはいけない」と言いきかせる。トトはその言葉通り、列車でロー マに向け旅立ち、30年帰郷しない。帰るのはトトの葬儀の時だけだ。
では、きことわは、常に過去に帰りたいと願う、いやその過去の時点からどこにも旅立っていない主人公のポルノなのだろうか。
幸か不幸か、私はこの手の作品が好物である。ラッキープールとかポロメリアとか月影とかだ。この小説にも、そんな魅力があるのは確かだ。解体の準備がほぼ終わり、二人でコーヒーと白湯を飲むシーン。
雨はきりなく落ち、敷石に撥ね返る音が続く。沈黙の中、こうした雨は気象学では何というのか。粗雑な言葉が永遠子の中でいくつか浮かんだ。確かに雨が降っているはずの庭は、照ったり曇ったり天気が変わっているようにも見える。瞬間と永遠とがもつれて、ふとしたうちに百年千年と経つようだった。
解説で町田康は、次のように書いている
それは普通は、フツーに凡庸で甘美な追憶に過ぎない。言い換えれば、誰もが見る脈絡のゴミ、単なる夢に過ぎない。しかるに作者はそれを見事な小説にした。(中略)本書は、官能という言葉の本来の意味での官能小説である。
では、きことわでは、この過去を耽溺することの是非をどう捉えているのだろうか?見事な官能小説なのだろうか?
夢を見る貴子、夢に追いつく永遠子
小説の冒頭に「永遠子は夢をみる。貴子は夢をみない。」とある通り、永遠子とは対照的に貴子は夢を見ない。
それは、自分という存在は、若くして急逝した母親の見ている夢の中の存在であると思っているからなのだが、永遠子と再会し、別荘の整理が済み、解体を待つだけとなったとき、貴子は自宅で入浴しながら初めて夢をみる。建物も敷石も取り払われ、すっかり更地となった別荘の上を月日が流れていく夢だった。
同じように、夢を見るだけだった永遠子の夢は現実に追いつく。永遠子は引きこもりのインキャではない。結婚して子供もいる。しかし、そんな現実はまるで夢のように存在感がない。どこか別の誰かを斜め上から第三者として眺めているようだ。しかし、25年ぶりの再会、別荘の解体の整理を経て、永遠子の現実は夢に追いつく。
つまりこれは、追憶の官能小説ではない。官能的ではあるが、追憶の、ではない。夢が現実に、現実が夢に溶け合い、永遠子と貴子は溶け合いきことわになる。
ちょっとこの本は売らない。読み返すかは分からないが、しばらく取っておく。
(No. 192)
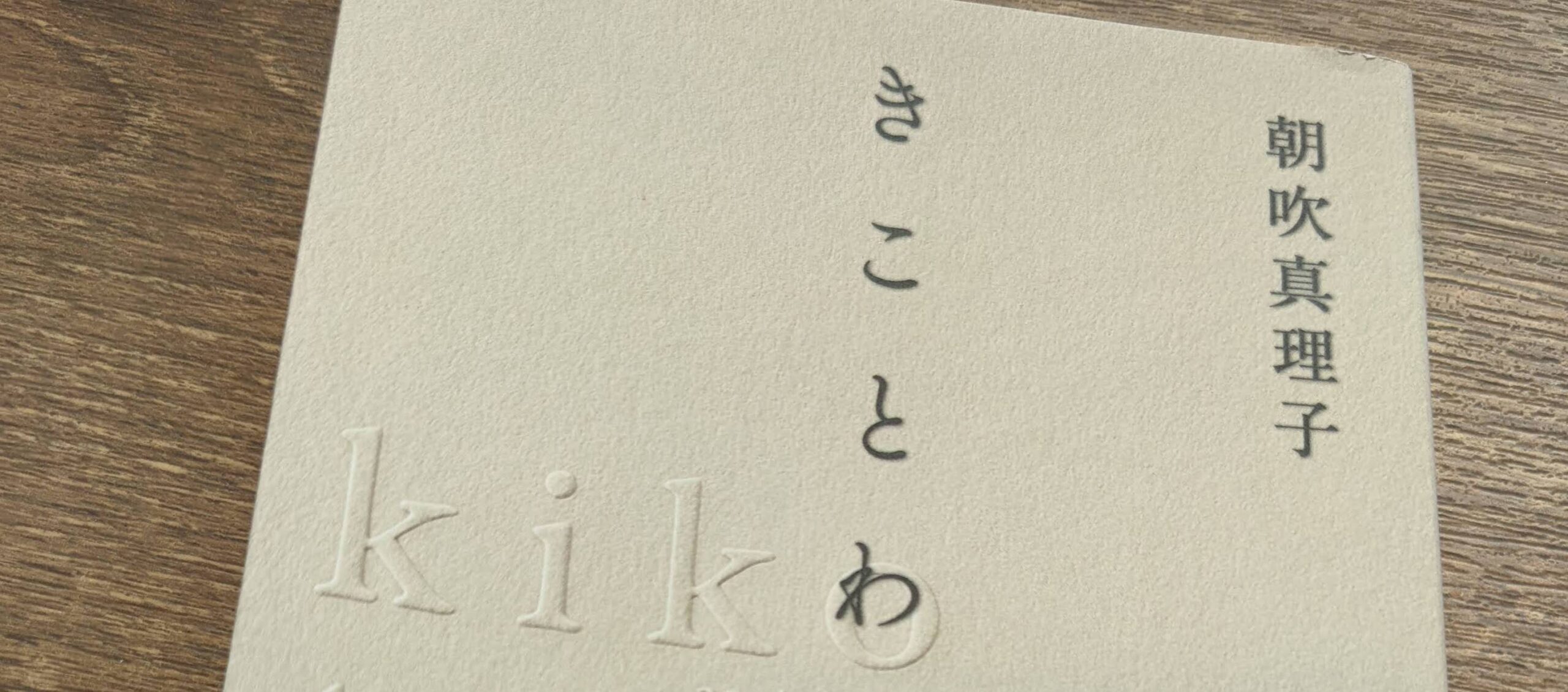



コメント