今年読んだ本、まとめ。「暁の宇品」や「一下級将校の見た帝国陸軍」もよかったが、ベストは、「死の貝」。現代の公衆衛生が過去の膨大な犠牲と研究に支えられていることを思い知った。
- 1 東京都同情塔
- 2 羆嵐
- 3 人に頼む技術
- 4 ビヨンド・リスク
- 5 デジタル・ゴールド
- 6 Web3の未解決問題
- 7 一下級将校の見た帝国陸軍
- 8 人生のレールを外れる衝動の見つけ方
- 9 岩壁よおはよう
- 10 いちばん優しいブロックチェーンの教本
- 11 BUTTER
- 12 ユニクロ
- 13 シニアになってひとり旅
- 14 燕は戻ってこない
- 15 死の貝 日本住血吸虫症との戦い
- 16 イーロン・ショック
- 17 バリ山行
- 18 春にして君を離れ
- 19 砂糖の世界史
- 20 猫を救うのは誰か ペットビジネスの「奴隷」たち
- 21 道頓堀川(再読)
- 22 暁の宇品
- 23 官僚たちの夏
- 24 ギヴァー 記憶を注ぐ者
- 25 ミラクルクリーク
- 26 一年前の猫
- 27 見ることの塩
- 28 エクスタシー(再読)
- 29 団地のふたり
- 30 経験学歴不問の職場で働いてみた
- 31 近畿地方のある場所について
- 32 家が好きな人
- 33 食事の戦略
1 東京都同情塔
主人公は、消毒されAIで文章を綴る美少年より、Fワードを連発する体臭のきついアメリカ人に心を開く。作者はこのアメリカ人のように、おキレイな綺麗事の価値観に中指を突き立てたかったに違いない。
— 半ねり (@hanbun_neri) January 27, 2024
2 羆嵐
三毛別羆事件、事件の残忍さもそうだが、入植者たちの貧しさに震える。東北で餓死寸前に追い込まれ、全てを捨てて移住した北海道でも、厳しい風雪に耐え、瘦せた土地を引っかく生活でこの事件。。。1915年12月の北海道。 pic.twitter.com/ISfXrMudmM
— 半ねり (@hanbun_neri) January 21, 2024
3 人に頼む技術
現代の業務は細分化されており、他人との連携(助け)が重要。しかし人は助けを求めることに非常にストレスを感じる。助けが必要かは外から見ると判断が付かない。だから積極的に求めていく必要がある。頼むうえで重要なのは内発的動機の刺激。相手に強いられていると感じさせてはいけない。だから謝るのもよくない。などなど、気づきはあるが、あまり実践できてない。
— 半ねり (@hanbun_neri) February 23, 2024
4 ビヨンド・リスク
読了
1️⃣なぜ山に登るのか?という問いの答えはほとんど出ている。生きるため
2️⃣日本は否定的な文脈で少し出てくるくらい。登山史においてそのくらいの存在
3️⃣トモ・チェセンのローツェ南壁は、なかったというのが結論。その他、スポーツ化やボルトなど思想的な議論が積み重なって現在を形作っている pic.twitter.com/cExQRP1NCG
— 半ねり (@hanbun_neri) February 18, 2024
5 デジタル・ゴールド
初期のクリプト(というと、ビットコイナーには怒られそうだが)の思想や文化的背景が感じられる。アングラで無政府主義的。そこまでパンクな生き方に賛成できる人は少数だろうが、マスアダプションは多様性の包摂とも言える。
— 半ねり (@hanbun_neri) March 20, 2024
6 Web3の未解決問題
単なる現状解説の章もあったが、根本的なところの議論もある。松尾先生と楠さんのパートは読み応えある。
— 半ねり (@hanbun_neri) March 3, 2024
7 一下級将校の見た帝国陸軍
組織自体の日常的必然で無自覚に「自転」していた。もうすぐ戦後80年な訳だが、現代の会社組織は帝国陸軍と驚く程変わっていない。「異なる組織を見て自身を相対化する」どころではない。「同じことやってんな」という印象を抱かざるを得ない。これは日本の宿痾だろうか?マッカーサーは日本を12歳の子供に例えたが、今の日本人は何歳だろうか…
— 半ねり (@hanbun_neri) April 21, 2024
8 人生のレールを外れる衝動の見つけ方
要領の良さを捨て、器用な立ち回りを捨て、合理的な選択を捨て、自分という存在を強烈にドライブする「衝動」に取り憑かれたいと思う人は少なくないはず。そういったものの見つけ方を期待したわけだが、結論としては「自己の中に深く潜りつつ、外部に心を開き、衝動の欠片を感受する」というフツーのものだった。魔法はないのだろう。
— 半ねり (@hanbun_neri) May 11, 2024
9 岩壁よおはよう
読んだ。クライマーは我の強い人間が多いからか、山岳会の人間関係がギスギスしている。が、全体的に具体的な登攀記録が多く、クライミングをしない人間には何のことかよく分からない。その意味でハセツネを既に知っているやや玄人向けの本。 pic.twitter.com/rem63eYqTW
— 半ねり (@hanbun_neri) May 19, 2024
10 いちばん優しいブロックチェーンの教本
この手の本、何回読んでもわからない。
よむ。おっさんを前面に出したデザインに好印象。 pic.twitter.com/yKz9dvvY42
— 半ねり (@hanbun_neri) June 1, 2024
11 BUTTER
日本人女性の出生率の低さは、女性が歴史的に最もジェンダーロールから解放されていることを示しているが、それは新たな地獄を生み出してもいる。BUTTERでは3人の女性が3つの地獄=家庭に入るという伝統的価値観、バリキャリによる経済的自立、男を支配する女性性の魅力という地獄が描かれる。バターは、この3つから自由になろうとする個人的欲望の象徴として位置付けられる。痩せている必要はない。綺麗である必要もない。誰かのためでなく自分のための幸福。
読んだ。感想別に書く。 pic.twitter.com/S2mCU5tAFw
— 半ねり (@hanbun_neri) June 22, 2024
12 ユニクロ
怒号の飛び交う会議、半分が売れ残る、全くいうことを聞かない海外現地従業員、聞いているだけで胃が痛いが「ごっこ」ではないことに羨ましさも感じる。あと、安定成長に満足できないパワーはどこから出てくるのか。
— 半ねり (@hanbun_neri) June 23, 2024
13 シニアになってひとり旅
読んだ。下川さんは旅を仕事にしたことで「自分の旅」を失ってしまった。そして「いつか僕の本が全く売れなくなったとき、自分の旅を取り戻せるだろうか?」とも。
この本は極めてパーソナルな旅である。そこに喜ばせるべき読者はいない。良くも悪くも下川さんが自分の旅を取り戻したようで嬉しい。 pic.twitter.com/aCuaUjiIY6
— 半ねり (@hanbun_neri) July 15, 2024
14 燕は戻ってこない
「私はもしかしたらモノになろうとして失敗する自分や彼女たちを見たかったのかもしれない。モノ化されようとするとき、彼女たちは最もモノから遠い存在になる。生々しく制御不能で、強かでずる賢く、欠陥だらけで、美しい。」
よむ#燕は戻ってこない pic.twitter.com/9MEmxHQeGh
— 半ねり (@hanbun_neri) July 7, 2024
15 死の貝 日本住血吸虫症との戦い
現代の公衆衛生が過去の膨大な犠牲と研究に支えられていることを思い知る。今年のベスト。
— 半ねり (@hanbun_neri) July 21, 2024
16 イーロン・ショック
イーロンと仕事をする、というのは一生の経験だろう。毎週やることを報告し、次週に結果を報告する。すべてトラッキングされ、提出していない人には追及が入るらしい。意外なマイクロマネジメントだが、その方が良いかもしれないと感じたり。あと本筋ではないが、この手の本にありがちな著者の武勇伝がほぼ皆無。逆に辛かった経験や失敗談、楽したい欲望を晒していて「こんな人でもそうなんだ」と共感してしまう。それは低位に安定という意味ではなく自分も、と前を向ける気がする。
— 半ねり (@hanbun_neri) August 12, 2024
17 バリ山行
主人公にとっての「本物」は山ではなく会社であり生活。しかし本当にそうだろうか?というのがテーマ。整備された登山道(会社)ではなく、道なき道の藪漕ぎこそ「本物」。だから主人公は二度とやらないと思ったバリ山行を続ける。まぁ分かるけど佳作って感じ。芥川賞も小粒だね。
— 半ねり (@hanbun_neri) August 17, 2024
18 春にして君を離れ
実家に帰り夫を迎える直前まで彼女は逡巡する。砂漠と太陽が照らす真実に向き合い赦しを乞うのか、これまでと同じように独善的な自分の世界に閉じこもるのか。彼女は後者を選ぶ。幸福は嘘と秘密でできているのかも知れない。しかしこのラストか…
— 半ねり (@hanbun_neri) August 25, 2024
19 砂糖の世界史
この人の頭にはどれだけの知識が蓄積されているのか空恐ろしくなる。この本の内容は氷山の一角で、その裏に執筆過程で削ぎ落とした膨大な情報の塊がある。私に直接関係するものではないが、少し世界を立体的に見られるようになった気がする。ほとんど忘れてしまったが。
よむ
砂糖の世界史 pic.twitter.com/RfO6gelnS6— 半ねり (@hanbun_neri) September 1, 2024
20 猫を救うのは誰か ペットビジネスの「奴隷」たち
基本的に市場原理は素晴らしいものだが、ペットの問題については外部不経済が大き過ぎる印象を受ける。数値規制は導入されたが実効性に課題を残すのは想像に難くない。自治体の労力に限界があり全数を適切に検査するなど不可能だろう。構造的に解決できないものか。
— 半ねり (@hanbun_neri) September 7, 2024
21 道頓堀川(再読)
もう何回読んだか分からない。当初は、ビリヤードの勝敗の行方を切り口にして書き始めたが、この小説が運命に抗おうとする物語なのだと気づいた時、ビリヤードの勝敗は大した問題ではないのだと気づいた。結果ではなく、姿勢の問題だから。
緑の小宇宙を輾転する血塗られた小動物たちの行方(宮本輝、道頓堀川のその後) https://t.co/DKVCcPU0nh
— 半ねり (@hanbun_neri) September 15, 2024
22 暁の宇品
宇品(うじな)という地名も聞いたことがなかったが、アメリカが原爆の投下地に広島を選んだ理由の1つが陸軍の海上輸送基地があったかららしい(海軍の呉ではない)。事実、日清日露、太平洋戦争と多くの兵士が宇品から戦地に向かった。日本軍のロジが破綻していたというのは有名だが、現場は結果を出そうと奮闘した。
読む『暁の宇品』。堀川さんは永山則夫の精神鑑定の本で知って以降「この人だから」という理由で読む貴重な人。 pic.twitter.com/JXPBKDWDVi
— 半ねり (@hanbun_neri) September 23, 2024
23 官僚たちの夏
読むのに時間がかかった。これを読んで官僚を目指そうという高校生の気持ちも分からなくはないが、自分たち(だけ)が日本経済を舵取りしなければ、といった勘違い感が強すぎる。アメリカでは一流の人材は民間に行くらしい。昨今の官僚離れは単に労働環境だけの問題ではない。もはや主役ではないのだ。
— 半ねり (@hanbun_neri) September 21, 2024
24 ギヴァー 記憶を注ぐ者
銃夢で、生きた馬のメリーゴーランドを思い出す。ある馬が手綱を引き千切って逃げ出すが、傷つき死んでしまう。「愚かな馬だ。メリーゴーラウンドの上を回っていれば死なずにすんだものを。」。そう言うノヴァ教授にケイオスは応える。「僕はそうは思わない。この馬は最後の数歩を自分の意思で歩いたのだ。」。良くも悪くも児童書。
読む
主人公はもうすぐ12歳になる少年。彼の住むコミュニティは一切の苦痛も不便もないまさしく理想郷。けれど、そこには何か重大なものが欠けている…12月、全ての子供が職業を授けられる「12歳の儀式」で、彼はコミュニティでただ一人の「記憶の器」【レシーヴァー】に任命されるのですが…。 pic.twitter.com/F9TK9Lqg4F
— 半ねり (@hanbun_neri) October 19, 2024
25 ミラクルクリーク
幸福は秘密と嘘で構成されているのであって、真実に意味があるのだろうか?と感じるなど。障害のある子の親の想い。移民の貧困。
読む。ミラクル・クリーク。Xの時間制限を設けてから代わりLINEの読書よオプチャに参加していて、そこで紹介されていた。韓国のステンレスの箸が使いにくいの同意。あれはなぜなのか? pic.twitter.com/84KTWcXUpi
— 半ねり (@hanbun_neri) October 26, 2024
26 一年前の猫
平坦な日常が奇妙に彩られていて羨ましい。どうすればこのような感性を得られるのか?文章も簡潔だが読ませる。こんな文章書けたらいいのに。
読む。一年前の猫。近藤聡乃さんは、ニューヨークで考え中がすごく良くて今でも本棚にある。アサリの酒蒸しを作っていると、パカッと開いた貝の中で子供が眠っている。みそ汁でも貝殻だけの貝はある。落ちてしまったのだろうが、そうではない可能性。 pic.twitter.com/M4lzl2Fhpu
— 半ねり (@hanbun_neri) November 4, 2024
27 見ることの塩
読んだ。見ることの塩。戦前にパレスチナに渡り国家建設に尽力したシオニストにとって、欧州に留まったユダヤ人は軽蔑対象であり、初代首相のベン・グリオンは、アウシュビッツの生存者を人間の屑と呼んだらしい。ユダヤ人社会内の差別など最初は結構衝撃だが段々複雑すぎてよく分からなくなってくる pic.twitter.com/WTmn3DtmWa
— 半ねり (@hanbun_neri) November 10, 2024
28 エクスタシー(再読)
昔から好きな作品だが、改めて読んでみてようやく物語全体を構造化し、テーマ性も意識できるようになった。
村上龍の『エクスタシー』にみる、「幸福な奴隷」からの脱却方法 https://t.co/O8VkM7OQA2
— 半ねり (@hanbun_neri) December 1, 2024
29 団地のふたり
ドラマを見たときは、ノエチとなっちゃんは、日常の豊さに気づくふりをすることで、非日常の可能性と終わりの悲しみから逃げていると感じた。小説は押し付けがましさがなくドラマより好感。
読んだ。ドラマに比べて日常の彩りの豊かさという押し付けがましさはなく、郷愁や感傷も少なく、淡泊なところに好感。同じ世代の女性であれば尚更だろうし、私にとっても切実なものになってくるだろう。 pic.twitter.com/38trkBxmTB
— 半ねり (@hanbun_neri) December 8, 2024
30 経験学歴不問の職場で働いてみた
令和版、求人の向こうの知らない世界。ビデオボックスでオナホを使う人は、使わない人に比べて部屋を綺麗に使う。ピンサロ嬢は目を伏せてツムツムばかりしている。肉体労働者の仕事中の話は9割がパチスロなど、妙なリアリティとインサイトがある。作業系は仕事としてやってみたい気がしていたが、作業だけしていればいいのではない。人間関係人間関係。。。
31 近畿地方のある場所について
本屋でたまたま手にとった。ネット上のアダルトサイトへの奇妙な投稿から始まる話が、こちらも妙なリアリティ。読んでいて素直に「怖い」と感じた珍しい体験だった。本を読んで感情を動かされること自体が少ないので貴重。
32 家が好きな人
休日は、「何かしなければ」、「充実して過ごさなければ」という変なプレッシャーがある。中途半端な向上心は大抵挫折して、無意味な罪悪感を覚えて終わることになるのだが、この本は家にいていいのだ。どこにも行く必要はない。それでいい。そう優しく肯定してくれる。それは、無根拠かも知れないし、必死で勉強している人もいるだろうが、それでも。
33 食事の戦略
魔法はない、って感じ。嫌々忘年会の幹事をしている状態から脱却できれば、と思ったが、積極的に人脈を形成していきたいと考えられない。Tipsは役に立つが良くも悪くも王道の正攻法で、「やっぱりそれやらなきゃダメ?」という感じ。飲み放題の店は酒の持ち込みOKは意外だった。話題作りになりそう。
読む。完全に仕事の本。 https://t.co/NAL8Rfaupl pic.twitter.com/26wWP7PFlE
— 半ねり (@hanbun_neri) December 21, 2024
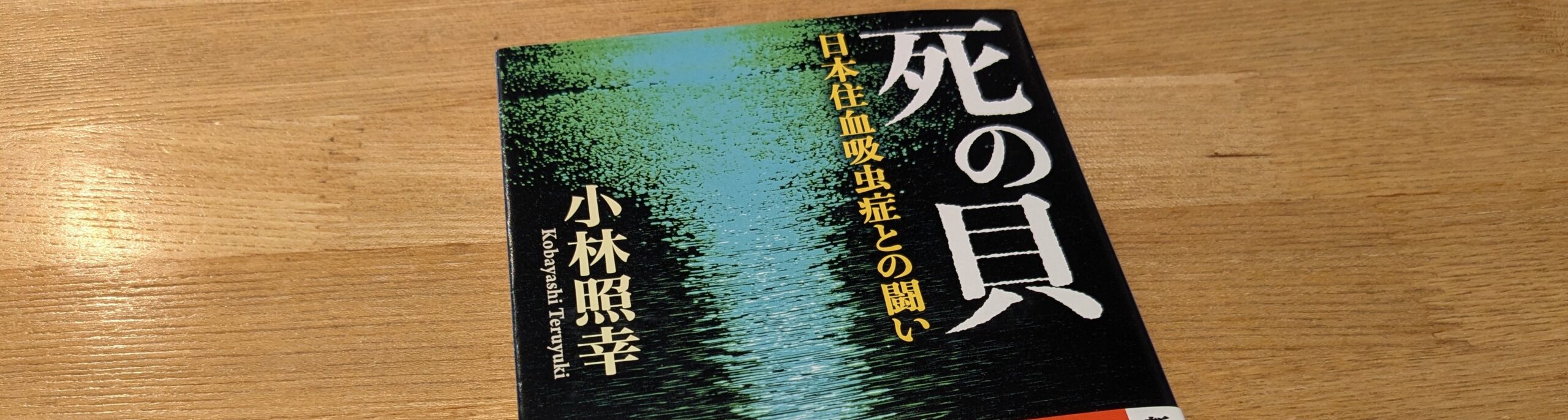
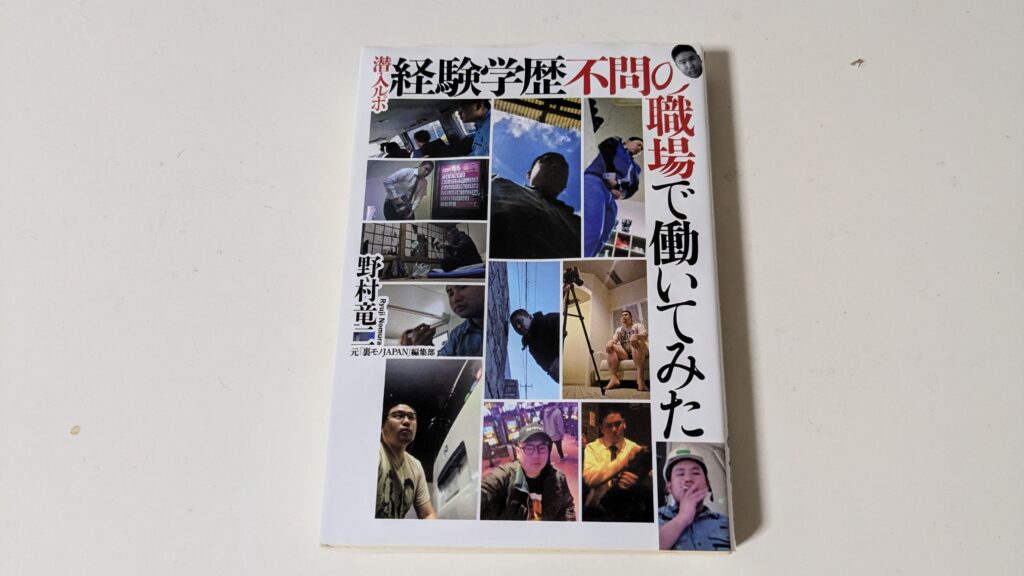
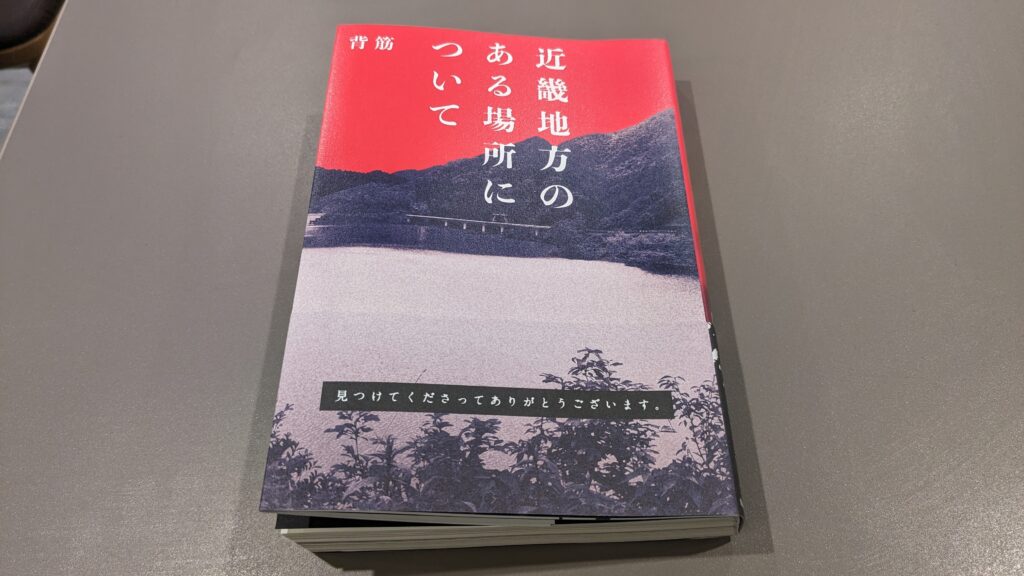
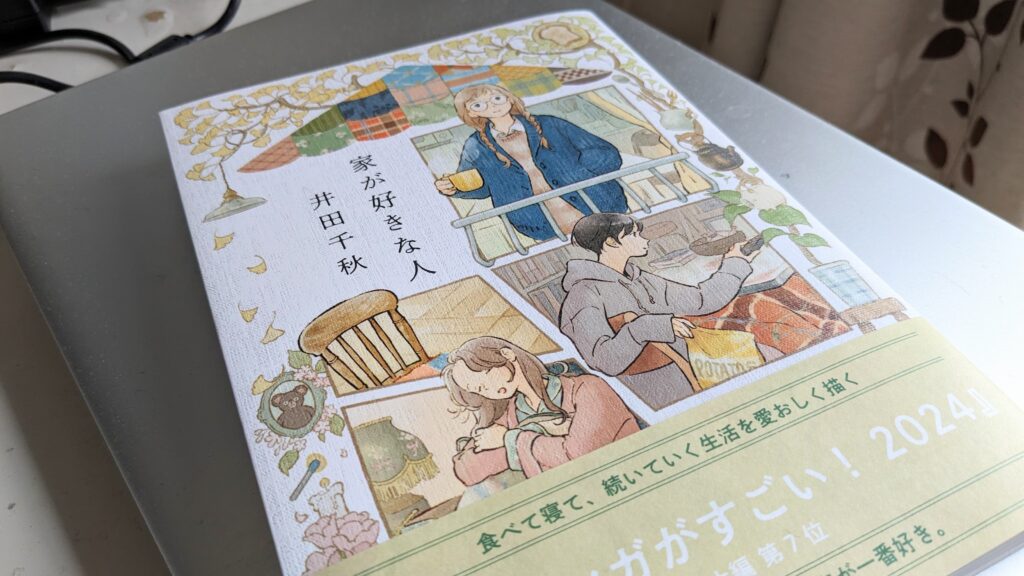


コメント